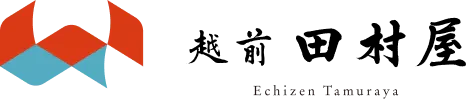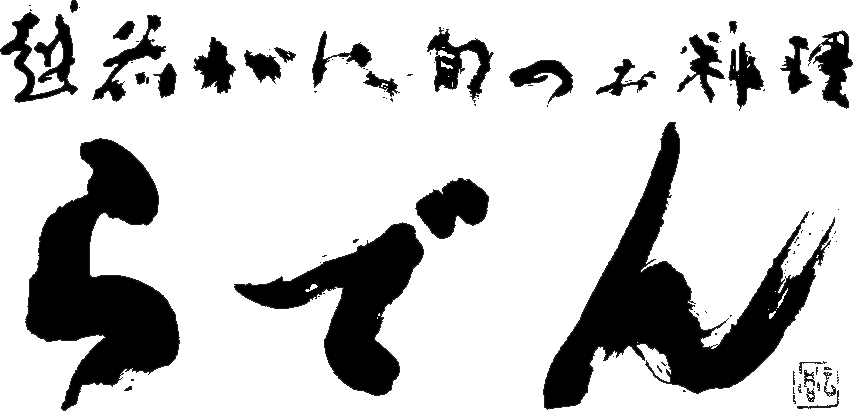日本海の豊かな恵みに支えられ、漁師町として発展してきた福井県。中でも「鯖(サバ)」は、古くから福井の食文化と人々の暮らしに深く根付いてきました。冬の越前ガニに並び、実は“鯖文化”も福井が全国に誇れる大切な地域資源のひとつです。近年では「鯖街道」や「へしこ」など、福井のサバにまつわる文化を求めて県外から訪れる人も増えています。
今回は、そんな福井の漁師町に息づく“鯖文化”の魅力を、歴史とともにご紹介します。
福井と鯖のつながり
福井は昔から新鮮なサバが水揚げされる地域として知られてきました。豊かな漁場で獲れるサバは、脂がのり、身が締まっているのが特徴です。沿岸の漁港では、地元の漁師たちが代々受け継いできた知恵と技で、季節に合わせて最適な漁を行い、新鮮なサバを供給してきました。
特に有名なのが「若狭湾」で獲れる鯖です。かつて都のあった京都まで、海で獲れたサバを運んでいたことから、京都と福井はサバで深く結ばれてきました。こうした背景が、福井の食卓にサバが欠かせない理由なのです。
鯖街道の由来
「鯖街道」という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
鯖街道とは、若狭湾で水揚げされたサバを、京の都・京都まで運ぶ際に使われた街道のことです。冷蔵技術がなかった時代、新鮮なサバを腐らせることなく運ぶために、漁師たちは一晩かけて山道を越え、全力で都へ届けたといいます。
塩で締められたサバは「生き腐れ」とも呼ばれるほど鮮度が落ちやすく、スピード勝負の輸送はまさに命がけでした。この輸送ルートはいつしか「鯖街道」と呼ばれ、現在では歴史文化として地域をつなぐ観光資源にもなっています。
鯖街道沿いには、かつての宿場町や名残を残すスポットが点在しており、今も旅人の足を止めています。
文化:半夏生とへしこ、サバ料理の魅力
福井にはサバにまつわる独自の文化が今も息づいています。
そのひとつが「半夏生(はんげしょう)」という風習です。半夏生は、夏至から数えて11日目を指す雑節で、農家にとっては田植えが一段落する時期。この日、福井では昔から「鯖を食べて夏の無病息災を願う」という風習があり、現在も半夏生の日にはスーパーや市場に“半夏生鯖”が並びます。
さらに、福井といえば保存食「へしこ」も有名です。へしことは、新鮮なサバを塩漬けし、米ぬかに漬け込んで長期間熟成させた伝統食品。昔は冷蔵庫のない時代に魚を保存する知恵として生まれましたが、今では塩味の奥にあるまろやかな旨味が多くの人を魅了し、焼き物やお茶漬け、パスタなど様々なアレンジレシピで親しまれています。
また、福井の鯖文化は“焼き鯖寿司”としても知られています。脂ののった鯖を香ばしく焼き、酢飯と合わせて押し寿司にしたこの名物は、県内の駅弁やお土産としても人気。福井を訪れたらぜひ味わいたい逸品です。
未来につなぐ福井の鯖文化
このように、福井の鯖文化は自然の恵みと漁師たちの努力、そして人々の暮らしが生み出した地域の宝です。
時代とともに物流や冷蔵技術は進歩しましたが、鯖街道や半夏生、へしこなどの文化は今も福井にしっかりと根付き、後世に語り継がれています。
最近では、地元の若い漁師や料理人たちが新しいサバ料理を開発したり、へしこの魅力を県外や海外へ発信したりする取り組みも増えています。
福井を訪れた際には、ぜひ漁港近くの食事処で新鮮な鯖を味わい、漁師町ならではの“福井の誇り”を感じてみてください。
越前水産の「浜焼き鯖」は、下記からご購入いただけます。(数量限定)
【楽天市場】
https://item.rakuten.co.jp/echizengani/t05-01/
【Yahoo!ショッピング – 通販】
https://store.shopping.yahoo.co.jp/echizengani/fu-5.html