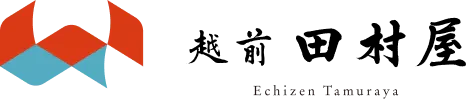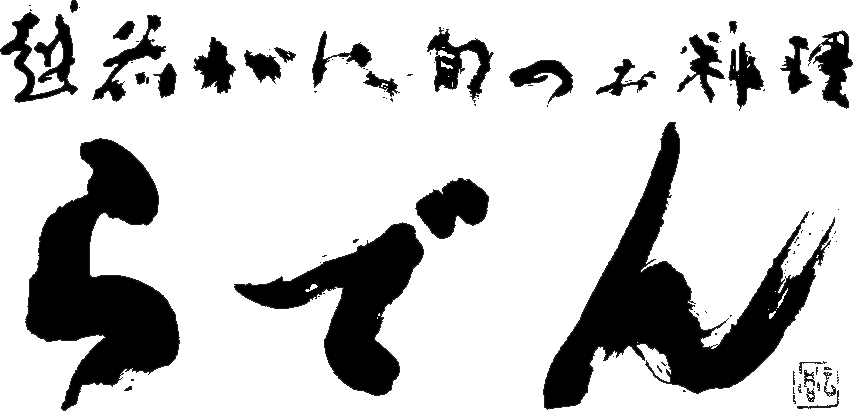へしことは? ─ 福井の誇る発酵食品
「へしこ」は、福井県を中心とした日本海側で古くから親しまれてきた伝統的な発酵食品です。主に鯖をぬか漬けにして熟成させる保存食で、独特の香りと深い旨味が特徴。ご飯のお供やお酒の肴として人気が高く、地元では家庭の味として親しまれてきました。
一見するとシンプルな「ぬか漬け魚」ですが、その裏には長い時間と手間、そして自然の力を活かした知恵があります。この記事では、「へしこができるまで」の工程を、順を追ってご紹介します。自分で作ることはなくても、そのプロセスを知ることで、へしこに込められた文化と職人のこだわりをより深く味わうことができるでしょう。
第一工程:塩漬け(一番漬け)
越前水産では、塩漬けの工程を「一番漬け」、ぬか漬けの工程を「二番漬け」と呼び、大きく2つの工程に分けてへしこの漬け込みを行っています。
越前水産のへしこ作りは、素材選びからすでに「職人の仕事」が始まっています。主役となる鯖には、脂がしっかりと乗り、身の引き締まった新鮮な個体だけを厳選して使用。魚の質そのものが、最終的なへしこの味を大きく左右するからです。

下処理は丁寧に。鯖を背開きにして内臓を取り除き、しっかりと水洗いをした後、鯖全体に塩がまぶされるように1尾1尾丁寧に塩漬けの工程を行います。
塩漬けの目的は大きく3つあります。
1つ目は、魚の余分な水分を抜き保存性を高めること。
2つ目は、血や脂による臭みを取り除くこと。
そして3つ目が、魚本来の旨味を内部にぎゅっと凝縮させることです。

およそ1週間から10日間の漬け込み期間で静かに熟成が進められます。
この時間が、へしこの味の基礎を築く非常に重要なステップとなるのです。
ここで仕込まれた鯖は、この後に続く「ぬか漬け」の工程で、さらに深い味わいへと変化していきます。
第二工程:ぬか漬け (二番漬け)
塩漬けを終えた鯖は、いよいよへしこ作りの要とも言える「ぬか漬け」の工程に入ります。
ここで使われるぬかにも、越前水産の並々ならぬこだわりが詰まっています。原料となる米ぬかは、契約農家から仕入れた福井県産こしひかり米のぬかのみを使用。香り・発酵力・魚とのなじみの良さまで考え抜かれた、へしこに最適な素材です。

このぬかに、越前水産独自の配合で唐辛子や生きた糀を加えます。この糀は、厳重な温度管理のもとで育てられた高品質な「生糀」で、魚の旨味を引き出しながら、深い発酵を促す重要な役割を担っています。
二番漬けは一番漬けで塩漬けした鯖の塩を落としてから特製ぬか床に丁寧に並べ、空気を遮断するように隙間なくぬかを詰めて密閉。ここで魚とぬかが初めて出会い、発酵のプロセスが本格的にスタートします。
最後に、調味液(詳細は企業秘密)を加え、へしこならではのまろやかな甘みと、深く重層的な旨味が育まれていきます。

そして、最大の特徴はその熟成期間の長さ。越前水産では、1年間という長い期間をかけて熟成させ、じっくりと発酵を進めています。時間をかけてゆっくりとぬかの成分が魚の芯まで染み渡ることで、表面から中心に至るまで味のムラがない、完成度の高いへしこが生まれるのです。

長期熟成を経たへしこは、身が艶やかな飴色に変わり、見た目にもその奥深さが伝わってきます。塩辛さは一切なく、口に入れると驚くほどまろやか。香り、旨味、甘みが一体となって広がり、噛むほどに奥行きを感じさせる味わいです。
完成したへしこ
一年間をかけて熟成された越前水産のへしこは、とても美しいです。魚の身は飴色に変化し、しっとりと艶を帯びた美しい仕上がり。表面のぬかを丁寧に落とし、お好みの大きさにカットして軽く炙れば、芳醇な香ばしさが立ちのぼります。
口に運んだ瞬間、へしこのイメージを覆すような優しい塩加減と、まろやかな甘み、そして深く複雑な旨味が広がります。「塩辛い保存食」という先入観は一切不要。むしろ、まるで時間が味になったかのような、穏やかで上品な味わいです。
白ごはんとの相性はもちろん、ペペロンチーノ風のパスタやへしこチャーハンなどのアレンジにもよく合い、近年では血圧抑制効果もあるとされ、健康食品としても注目されているひと品です。
まとめ
へしこは、「ただの漬け魚」ではありません。塩漬けからぬか漬け、そして一年にも及ぶ長期熟成という工程を経て、ようやく完成する発酵食品です。その過程には、素材へのこだわり、温度と時間の見極め、そして職人の経験が詰まっています。
越前水産のへしこは、ひとつひとつが丁寧に仕込まれ、目には見えない「時間の重なり」を味に変えていきます。だからこそ、ひと口食べるだけで、どこか懐かしく、心がほっと和むような味わいが広がるのです。
へしこがどのようにできあがるのか。その工程を知ることで、目の前にある一切れのへしこが、より深く、美味しく感じられるはずです。次にへしこを手にする時は、その背景にある伝統と職人の手仕事にも、ぜひ思いを馳せてみてください。